作曲家についてのクイズです。気軽に解いてください。(少し難しめ)

この中でローマ賞を受賞したことがあるのは誰でしょう。

制限時間:無制限

難易度:
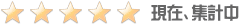

出題数:4人中

正解数:0人

正解率:0%


作成者:オルケスト (ID:21439)

出題No:16986
最高連続正解数:0 問
現在の連続記録:0 問

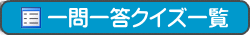
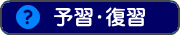
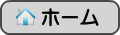

予習・復習/一問一答クイズ
出題文をクリックでクイズにチャレンジ!
すぐに答えを見たい場合は「解答を表示する」をクリックしてください。
こちらで学習をして、このクイズ・検定の合格を目指しましょう!
①クロード・デルヴァンクール
②デジレ=エミール・アンゲルブレシュト
③ギヨーム・ソーヴレー
④シャルル・トゥルヌミール
解答を表示する
正解:①
解説:正解は、クロード・デルヴァンクールです。1888−1954のフランスのピアニスト・作曲家で彼はパリ音楽院学生オーケストラを設立し、音楽家の国民前線においても活動しました。またローマ大賞次点のカンタータ「ヤニッツァ」などを作曲しています。
①カール・フリューリンク
②タウデシュ・シェリゴフスキ
③イグナツィ・パデレフスキ
④ソフィー=カルメン・エックハルト=グラマッテ
解答を表示する
正解:②
解説:正解は、タウデシュ・シェリゴフスキ(1896−1963)です。ポーランドの作曲家で、1951−1954年まではポーランド作曲家連盟の議長を務めました。また、4つのポーランド舞曲なども作曲しています。
①モーリス・デュリュフレ
②ヴァルター・ラブル
③ポール・ラドミロー
④シャルル・ケクラン
解答を表示する
正解:エルネスト・ファネリ
解説:正解は、エルネスト・ファネリ(1860−1917)です。彼はその時代における革新的な「交響的絵画」を作曲し、当時音楽雑誌などにもセンセーションを起こしました。しかし、彼は1894年には作曲の筆を折っており、以降作曲を再開することはありませんでした。
①エルネスト・ファネリ
②ジェルメーヌ・タイユフェール
③マリー・ジャエル
④リリ・ブーランジェ
解答を表示する
正解:④
解説:正解は、リリ・ブーランジェ(1893−1918)です。彼女は若くして才能を開花させ、1913年にはカンタータ「ファウストとエレーヌ」でローマ大賞を受賞しました。しかし、2歳で気管支肺炎を発症したことをきっかけに腸結核を併発し、24歳の若さでこの世を去りました。
①フェリクス・ノヴォヴィエイスキ
②ジグムント・ストヨフスキ
③ミェチスワフ・カルウォーヴィチ
④ジグムント・ノスコフスキ
解答を表示する
正解:①
解説:正解は、フェリクス・ノヴォヴィエイスキ(1877−1946)です。彼はベルリンでマックス・ブルッフに師事し、クラクフ芸術協会の芸術監督も務めました。また作曲家であると同時に、指揮者、教師、オルガン奏者の肩書きも持っていました。
①エルンスト・ミエルク
②セシル・シャミナード
③エルッキ・アールトネン
④エイナル・エルグルンド
解答を表示する
正解:①
解説:正解は、エルンスト・ミエルク(1877−1899)です。彼は、ベルリンでマックス・ブルッフに個人指導のもと作曲を学び、ピアニストとしても活躍しました。1897年には交響曲ヘ短調が初演され、シベリウスの交響曲第1番の作曲への刺激を与えたという風説もあります。しかし、肺結核により22歳の誕生日を目前にしてスイスにて客死しました。
①ハンス・ロット
②テオドール・デュボワ
③ジョゼフ・カントルーブ
④ジャン・ユレ
解答を表示する
正解:③
解説:正解は、ジョゼフ・カントルーブ(1879−1957)です。彼はフランスの作曲家・音楽学者であり、オーヴェルニュ民謡に管弦楽法をまとわせた歌曲集が有名です。1925年には数人のオーヴェルニュ出身の若者たちと文化団体「ラ・ブレ」を設立し、郷里の民謡や景勝地を広めようと尽力しました。彼自身、農民の唄は情緒や表現においては最も純粋な芸術の水準までしばしば到達していると信じ、活動を続けていました。
①アルベール・ルーセル
②ガブリエル・デュポン
③アレクシス・ド・カスティヨン
④デオダ・ド・セヴラック
解答を表示する
正解:④
解説:正解は、デオダ・ド・セヴラック(1872−1921)です。彼は、郷里ラングドックの伝統音楽に深く根付いた作品を創作し、色彩豊かな表現が使われる個性的なピアノ曲が有名になっています。
①エッフェル塔の婚礼調度
②エッフェル塔の蓄音機
③フレデリック・デランジェ
④エッフェル塔の銀婚式
解答を表示する
正解:エッフェル塔の花嫁花婿
解説:正解は、エッフェル塔の花嫁花婿です。これはフランス6人組(ルイ・デュレを除く)によって合作されたバレエ音楽で、1890年代に完成したばかりのエッフェル塔が舞台の物語になっています。花嫁花婿の他に、電報、蓄音機、将軍、写真機、水着美女などが登場します。
①ジェンヌ・ドゥメッシュー
②エルネスト・レイエ
③ピエール・シェフェール
④ギュスターヴ・シャルパンティエ
解答を表示する
正解:④
解説:正解は、ギュスターヴ・シャルパンティエ(1860−1956)です。ジュール・マスネに師事し、1887年にはカンタータ「ディドー」でローマ大賞を受賞しました。また、ミミ・パンソン音楽院を開設し、女性労働者のために無料で音楽と舞踏を教えたそうです。
①アストル・ピアソラ
②エリー・シーグマイスター
③エッフェル塔の花嫁花婿
④クルト・ヘッセンベルク

登録タグ

関連するクイズ・検定

その他のクイズ・検定

その他・関連するクイズ
このクイズ・検定や問題に関連するクイズを出題しております。出題文をクリックするとクイズにチャレンジできます。
すぐに答えを見たい場合は「解答を表示する」をクリックしてください。
説明:クラシック作曲家のうちJ.S. バッハについての質問です。
①1644年
②1685年
③1724年
④1712年
①マーク・ブリッツスタイン
②ブランデンブルク協奏曲第3番
③無伴奏チェロ組曲第5番
④平均律クラヴィーア曲集第1巻
①42曲
②24曲
③36曲
④64曲
①ゴルゴタ
②管弦楽組曲第2番
③アトスの山
④ヘルツルの丘
①エルサレム
②ミヒャエル教会(ハイデルベルク)
③聖トーマス教会(ライプティヒ)
④聖シュタット教会(カールスルーエ)
①「われらは涙流してひざまずき」
②「見よ、イエスはわれらを」
③「ああ、いまやわがイエスは連れ去られぬ」
④「われら、信仰の道を歩め」
①4曲
②5曲
③8曲
④フラウエン教会(ドレスデン)
解答を表示する
正解:①
解説:BWV537を含めた数です
①第4楽章
②第1楽章
③第2楽章
④第3楽章
①教会カンタータ「神われらとともになかりせば」
②教会カンタータ「主よ、深き淵よりわれ汝を呼ぶ」
③6曲
④教会カンタータ「心と口と行いと生活で」
①「いざ来ませ、異邦人の救い主よ」
②「全地よ、神に向かいて歓呼せよ」
③「神はいにしえよりわが王なり」
④「キリスト者よ、この日を銘記せよ」
①「イエスよ、汝わが魂を」
②「偽りの世よ、われは汝に頼まじ」
③「われらが神は堅き砦」
④教会カンタータ「神の時こそいと良き時」
①平均律クラヴィーア曲集 第2巻
②「おお永遠よ、いかずちの声よ」
③クラヴィーア練習曲集 第2巻
④クラヴィーア練習曲集 第4巻
①第4番
②第6番
③平均律クラヴィーア曲集 第1巻
④第8番
①第6番
②第5番
③第3番
④第5番
①27曲
②16曲
③35曲
④第4番
①43曲
②ヴァイオリン協奏曲 第1番
③チェンバロ協奏曲 第3番
④オルガン協奏曲 第4番
解答を表示する
正解:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番
①管弦楽組曲 第1番
②ヴァイオリン協奏曲 第2番
③チェンバロ協奏曲 第5番
④無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番